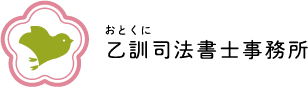開業以来、大山崎町物件や長岡京市物件に限らず、ありがたいことに亀岡市や城陽市、京都市、さらには府外の物件についてもご依頼を頂いております。
今回は京都市の物件について特別に注意しなければならない事項がございましたので、記事にしてみようと思いました。
前半は名寄帳全般についてのお話で、後半は京都市の名寄帳に関するお話です。
■名寄帳(なよせちょう)について
相続登記をご依頼頂いた際、当事務所では必要書類として「名寄帳」の取得をご案内しております。名寄帳(なよせちょう)とは、所有者別に土地または家屋に関する情報をまとめた市区町村が作成する台帳です。亡くなられた方が所有していた特定の市区町村内にある全ての不動産とその評価額が記載され、その写しを法務局に提供して相続登記申請を行います。
当事務所が名寄帳を代行取得することもできます。(実費を除き、代行取得費は別途請求しておりません。余談ですが、大山崎町と長岡京市は実費も無料です。)
毎年5月に役場の税務課から送付される固定資産税の課税明細書の写しを提供して相続登記申請を行うこともできますが、それでもなお名寄帳を別途取得していただく理由は、固定資産税の課税明細書には公衆用道路や保安林といった「非課税地」が記載されていない一方で、名寄帳には非課税地も含め、すべての不動産が記載されるためです。これにより、非課税地の相続登記漏れを防止することができます。
非課税物件の相続登記漏れが発生すると、場合によっては大変なことになりかねません。
かつて相続登記申請を行った時の遺産分割協議書と印鑑証明書を探していただく必要があり、それらが見つかったとしても、遺産分割協議書の内容に漏れていた物件が含まれていなければ、再度その物件について遺産分割協議書を作成し、現在の相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。(例えば20~30年前の相続登記で登記漏れが起きていれば、数次相続の可能性もあり、相続人が増えてしまい、ハンコ集めが大変になります。)
話を戻しますが、名寄帳を取得していれば登記漏れを必ず防げるかというと、実はそうではありません。
共有者が多すぎる物件については、自治体が共有者のひとりひとりを把握しきれていないことが多く、また、職員のミスにより年度更新の際に課税明細書や名寄帳から物件が抜け落ちてしまうこともあります。(自治体に指摘して修正していただいたことがあります。)
このように、名寄帳を取得しても必ずしも万全というわけではありませんが、自治体が把握している限りにおいては非課税地も記載されるため、できる限り登記漏れを防止する観点から、名寄帳の取得をご案内しております。
■京都市の名寄帳について
京都府の各自治体では、京都市を除き、名寄帳を取得すると保安林や公衆用道路といった非課税地が記載されます。しかし、京都市が発行する名寄帳には非課税地が記載されません。
そのため、京都市物件の登記手続きにおいては登記漏れが非常に起こりやすい状況であり、この点については京都司法書士会が定期的に京都市長に対して、固定資産税の課税明細書や名寄帳に非課税地を記載するよう要望書を提出しているところです。
名寄帳を取得しても非課税地が記載されない以上、現在のところ、京都市内の物件について相続登記の登記漏れを防止する施策としては、以下のような方法が考えられます。
・亡くなられた方が所持していた権利証をご持参いただき、物件欄を確認する。
・所有していた物件の近隣(特に前面道路)の登記情報を閲覧する。
これらの方法をとるにあたっては、公図の閲覧や物件の特定(目星の付け方)が必要となります。この点について司法書士は精通しておりますので、相続登記はぜひ司法書士にご依頼いただければと思います。